
私たちも歳をとってきたけれど、両親もかなり高齢になってきたね。もし認知症になったらどうしよう・・・
そうだね。認知症になって意思疎通が取れなくなると、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなるから困るよね。高齢化は避けては通れないしなあ。


介護が必要になったらお金もかかるから預金の引き出しができないのは困るね。今からできる、何かいい対策はないかな?
それなら「家族信託」はどうなかな?家族の財産を守る新しい仕組みだよ!

私はFPをしている2じろう6といいます。私も40代になり、親も高齢になってきました。
超高齢化社会の日本。介護、認知症の問題は避けては通れない問題です。医学の発展により、寿命が延びてきました。喜ばしいことでもありますが、介護、病気等で意思疎通が取れないのはリスクになります。長い期間、介護、認知症状態が続くのはとても大変なことです。
そんな“もしも”に備える制度として注目されているのが、家族信託(民事信託)です。
本記事では、家族信託のしくみ・メリット・デメリット・成年後見制度との違い、費用面までを分かりやすく解説します。
この記事を読めば、親が認知症になった場合でも、財産を守ることができます。「まだ先のことだから」と思わずに、知識として知っておくと、きっと役に立ちます。
・家族信託は、認知症に備えて財産を家族で守る制度
・成年後見よりも柔軟で、自由度が高い
・法的な力もあり、正しく使えばとても心強い仕組み
・費用面では家族信託は一度きりの費用で、成年後見は継続的な費用がかかる
目次
1. 家族信託とは?
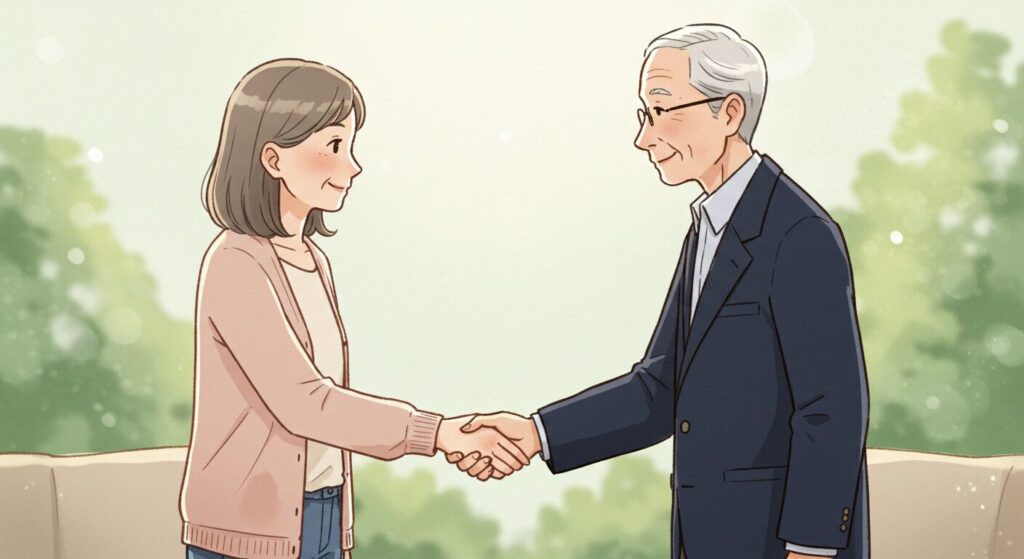
家族信託とは、親(委託者)が子ども(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せる制度です。
親の判断能力があるうちに契約を交わし、もし認知症などで判断力が低下しても、
信託契約に沿って子がスムーズに財産を管理できるようになります。

家族信託は、2007年施行の信託法という法律によって制度化されています。
そのため、口約束ではなく、正式な「信託契約書」を交わせば、民法上の契約として効力が発生します。
1.1 家族信託でできること(法的な効力の例)
| 例 | 法的な効力 |
|---|---|
| 認知症になっても、子が親の代わりに不動産を売却できる | 不動産の「名義」が信託された子に移っているため可能 |
| 信託契約に沿ってお金を管理し、親の生活費に使える | 受託者(子)は契約に基づいて財産を使える |
| 遺言のように、親の死後に財産の行き先を指定できる | 「受益者の変更」や「残余財産の帰属先」を契約で指定できる |

いろいろなことを代わりにできるようになるんだね。
1.2 家族信託の具体例
【具体例①】実家の管理を子に任せたい父と息子のケース
🧓登場人物
- 父:78歳。長年住んでいる一戸建てに一人暮らし。
- 息子:50歳。別の市に住んでいるが、実家の管理が心配になってきている。
🏠背景
父はまだ元気だが、今後の体調や認知症のリスクを考え、実家をどうするか考え始めている。将来は売却や賃貸も選択肢に入れているが、判断能力が落ちてしまったら、父の名義のままでは何もできなくなる。息子が実家を管理したくても、法的な手続きができなくなることを不安視している。
✅対応:家族信託の活用
父が元気なうちに、実家の土地と建物を信託財産として設定し、息子を受託者とする信託契約を結ぶ。信託契約の中で、実家の修繕・維持管理、将来的に売却や賃貸も可能とする条件を明記しておく。
📌結果
- 父は住み続けることができ、名義は信託の対象になるが「住む権利」は守られる。
- 息子は受託者として、必要な修繕や売却手続きをスムーズに行える。
- 認知症になっても、息子が事前の契約に沿って動けるため、実家の資産価値を守ることができる。
【具体例②】預貯金の管理に不安を感じる母と娘のケース
👩🦳登場人物
- 母:77歳。ひとり暮らしで慎ましく生活しているが、将来の判断力の低下が心配。
- 娘:45歳。近くに住んでおり、母の通院や日常の買い物をサポートしている。
🏠背景
母の名義の銀行口座には1,000万円以上の預貯金があり、介護が必要になったときの費用に備えている。しかし、もし母が認知症になったら、その預金は娘が勝手に引き出せなくなる。成年後見制度を使うのは手間や費用がかかりすぎるのがネック。
✅対応:家族信託の活用
母が元気なうちに、預貯金の一部(たとえば500万円)を信託財産として設定し、娘を受託者とする信託契約を締結。娘はその資金を、母の生活・介護に必要な支出のために使えるようにする。
📌結果
- 母が認知症になっても、娘が信託財産(500万円)を使って医療費・介護費用の支払いができる。
- 銀行凍結の心配がなくなり、母も娘も安心。
- 成年後見制度のような報告義務や監督人報酬も不要で、実務が軽い。
2 家族信託のメリット・デメリット
家族信託のメリット・デメリットを見てみましょう。
2.1 家族信託のメリット
- ✅ 認知症になっても、子が財産管理・売却できる
- ✅ 裁判所の関与がなく、自由度が高い
- ✅ 遺言のように「死後の財産の受け取り先」も設定できる
- ✅ 成年後見よりも柔軟で、費用も抑えられるケースが多い
2.2 家族信託のデメリット・注意点
- ⚠️対象財産は「契約で指定したもの」だけ(全財産ではない)
- ⚠️ 契約書のミスや曖昧な表現でトラブルになることも
- ⚠️ 信託財産の運用・管理には責任が伴う(受託者の義務)
3 家族信託と成年後見制度との違い
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 開始のタイミング | 元気なうちに契約 | 判断能力が低下した後 |
| 管理対象 | 指定した財産のみ | すべての財産 |
| 柔軟性 | 高い | 低い(裁判所の監督あり) |
| 裁判所の関与 | なし | 常にあり |
| 費用面 | 初期費用のみ(専門家への依頼) | 継続的な後見人報酬あり |
✅ 家族信託は「予防」
✅ 成年後見は「事後対応」

家族信託は、管理する財産をきちんと契約書で決めておけば、裁判所の管理もないので、自由度が高いです。
4 家族信託と成年後見制度の費用比較
費用面では、家族信託と成年後見制度には大きな違いがあります。以下に、それぞれの制度にかかる費用を比較しました。
4.1 家族信託の費用
1. 初期費用
家族信託を始めるためには、信託契約書の作成が必要です。これには専門家(司法書士・弁護士など)のサポートが一般的です。
その費用は財産の規模や契約内容により異なりますが、数万円~数十万円が相場です。
また、不動産の登記が関わる場合には、登記費用も発生します。
2. 運用・管理費用
信託契約後は、受託者(子どもなど)が財産を管理します。受託者が家族の場合は、管理費用はかかりませんが、外部の専門家に管理を依頼する場合には管理報酬が発生します。
3. 終了時の費用
信託契約終了時には、相続税申告や登記変更などに費用がかかることがあります。
4.2 成年後見制度の費用
1. 後見人報酬
成年後見制度では、後見人(家庭裁判所が選任)に対して、月々の報酬が発生します。
その金額は財産の規模や地域によって異なり、一般的には月額1~10万円程度です。
2. 申立費用
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要で、その費用は数千円~数万円程度です。
また、申立てを弁護士や司法書士に依頼した場合、その報酬が別途かかります。
3. 運用費用
成年後見人は財産を管理するための手数料を受け取ります。財産が多い場合、手数料も高額になることがあります。
4. 終了時の費用
成年後見が終了する際にも、手続き費用や最後の報酬が発生します。
4.3 費用比較表
| 費用項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 数万円~数十万円(専門家への依頼) | 数千円~数万円(申立て費用+弁護士費用) |
| 月額管理費用 | なし(受託者による管理) | 月額1~10万円程度(後見人報酬) |
| 追加費用 | 財産規模により登記費用や管理費用あり | 財産規模に応じた管理報酬や手数料あり |
| 終了時の費用 | 税務手続きや登記変更に費用がかかる | 終了手続きにかかる費用(後見終了報酬) |

家族が財産を管理するなら、家族信託のほうが費用面も安く済みそうね。
5 家族信託の始め方(5ステップ)
- 家族で話し合う
└ どの財産を、誰に、どう任せるかを整理 - 専門家に相談する
└ 家族信託に強い司法書士・弁護士・専門サービスなど - 信託契約書を作成
└ 財産の管理方法・終了条件なども明記 - 不動産があれば信託登記
└ 登記をしないと名義変更ができません - 運用スタート
└ 契約に基づいて受託者が財産を管理
6 専門家選びに迷ったら|家族信託サービス「おやとこ」がおすすめ
「信託の内容がよくわからない」「どこに相談すればいい?」という方には、
おやとこ(トリニティ・テクノロジー株式会社)という家族信託専門サービスの利用がおすすめです。
- ✅ 無料で相談できる(LINEや電話)
- ✅ 家族信託に特化した専門家が対応
- ✅ 相談者の多くが「親のため」に利用
\ 将来の不安を、今できる安心に /
👉 おやとこ公式サイトはこちら
7 まとめ
- 家族信託は、認知症に備えて財産を家族で守る制度
- 成年後見よりも柔軟で、自由度が高い
- 法的な力もあり、正しく使えばとても心強い仕組み
- 費用面では家族信託は一度きりの費用で、成年後見は継続的な費用がかかる
家族信託は、FPから見ても、成年後見より使いやすく、家族とその財産を守るためのとても素敵な制度です。しかし、自分で契約書を作るのは難しく、専門家のサポートが必要です。

「おやとこ」は、家族信託に強い専門家にオンラインで相談できるサービスなので、安心して相談することができます。無料なので、「親の認知症が心配」という方は一度相談してみてください。
お互いが元気なうちにこそ、“親のための準備”を始めましょう!
あなたの行動が、親の安心と、家族の未来を守ることにつながります。
この記事が、相続で悩む方の手助けになれば幸いです。以上、2じろう6でした!







コメント